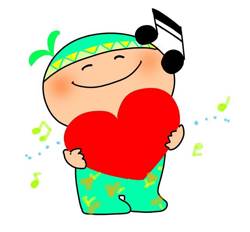私のお袋が既に死んでもう20年近くになろうか?
親父が死んだ翌年に亡くなった。
息子・娘を10人も生んで育てた。
車で30分以内には娘、息子は住んでいたが、日々は広い家に一人で住んでいた。
体重が重かったため、足を悪くしていた。
買い物は自分で出かけていたが、やはり、外出したくはないようで、一日家にいることが多かった。
ある夏のお盆の日、私は横浜から久々に家内と子供たちを連れて帰った。
孫はその時は既に18人いたが、私の子ども二人で20人目。
孫の顔を見るとやはり目を細めてみていたのを思い出す。
5日間があっという間に経ち、明日、横浜に帰るという時、私はお袋と話をした。
いつも、一日が終わると、夕方仏壇に向かい、死んだ親父と話をするのだと言う。
その時が一番うれしいと言うのだ。
その後で、簡単に夕食を済ませ、日記を書くのだと言う。
私はその日記帳を見せてくれというと、茶箪笥の引き出しから手帳を出した。
小さな手帳だった。
小さい字で一日のことが書いてある。
私は、直ぐに家内に頼み、大学ノートを買ってきてもらった。
私はそのノートをお袋に渡し、「この方が書きやすいから」と言った。
翌日私は子供たちを連れて横浜に帰った。
流石に、別れが辛かった。涙も止まらなかった。
子供達は私の涙を見て不思議に思ったことだろう。
それから、2か月が経った。
そして、ある晩、田舎の兄貴から、「お袋が危篤だから・・・」と電話があった。
私は、来るべき時が来たと直感した。
病院に着いた時は人工心肺をつけられ、無理やり呼吸をさせられていた。
その晩は私は病院に泊まった。
夜中の3時頃、待合室のベンチで転寝をしていた時、看護婦がやって来た。
看護婦に連れられて行くと、医者が、もう血圧も50以下になってしまった。
「どうしましょうか?」と問われたので、私は、
「もう、人工心肺をはずしてやってくれ」、と頼んだ。
その瞬間、お袋は天に召されていった。
それから数日葬儀の準備でバタバタしていた。
私は、家内と子供たちと一緒に仏壇に手を合わせ、家を離れた。
その時、お袋に渡した日記帳の大学ノートと手帳を持ち帰った。
横浜に帰り、私はじっくりと大学ノートを読んだ。
そこには、我々が別れたあの日から2カ月のお袋の日記がびっしりと書かれていた。
その中に、
「今日は、足が痛かったから、おじいちゃんに話に行く時、杖をついて行った。」
と書かれていた。
家の中の仏間に行くのに杖をついて行ったのかと思った瞬間、涙が流れた。
あの大学ノートをプレゼントとして渡したのではないが、それが、私のプレゼントとなった。
しかし、それがお袋からの我々の宝になった。