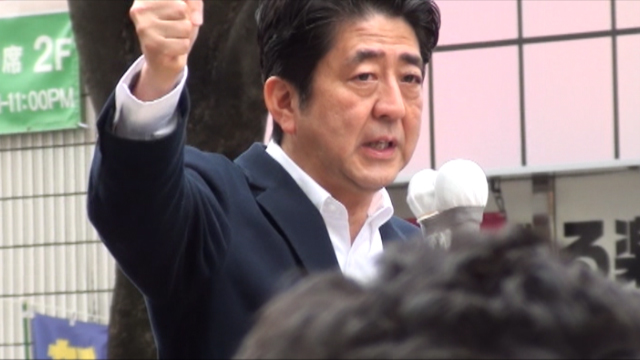今年のノーベル平和賞授賞式が10日、ノルウェー・オスロの市庁舎で行われた。
パキスタンのマララ・ユスフザイさん(17)=英国在住=史上最年少での受賞。
受賞演説でマララさんは、
「賞は私だけのものではない。
教育を求める忘れられた子どもたち、
変化を求める声なき子どもたちのものだ」
と強調した。
「なぜ“強い”といわれる国々は、
戦争を起こす上ではたくましいのに、
平和をもたらすことに弱腰なのか。」
「戦車を簡単に造るのに、
学校を造るのはなぜこれほど難しいのか」
「今こそ行動に移す時。
政治家や世界の指導者だけでなく、
私たち全てが関わらなければならない。
子どもたちが工場で過ごし、
戦争で命を落とし、
学校に行けずにいるのを、
これで終わりにしよう」
と呼び掛けた。
マララさんは賞金の全額を自身の基金に寄付した上で、
故郷に学校を建設する意思も明かした。
「私の村には女子の中学校がない。
友人が教育を受け、
夢をかなえる機会を得られるようにしたい」
と語った。
イスラム過激派による女子教育抑圧を告発したマララさんは、
2012年、下校途中にこの過激派から頭を銃撃され重体となったが、
事件後に搬送された英国の病院で一命を取り留めた。
マララさんの一言一言に感銘を受ける。
One teacher, one child, one book, one pen can change the world.
この言葉は真のリーダーの言葉である。