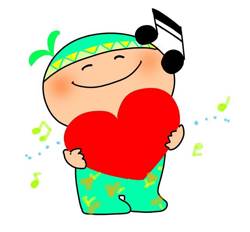私が小学校を終えるまでは、家族四人の生活に、電燈は四十燭光が二つだけだった。一燈だけの家も多かったので、普通だったのだろう。
家の建坪は、一階が四十坪位、二階が十坪位で、畳の部屋が五つと、板張りの部屋が二部屋あった。土間はかなり広く、納屋と小屋が別に建っていた。夜になると暗い所ばかりだった。
6 畳の居間に続いて、6畳の板張りがあり、板張りの部屋で、家族は食事をしていた。
一人ずつ箱型のお膳を持っていて、お茶碗もお箸もお自分の物が、その中に入れてあった。お膳の蓋を起こして、その上に食器を並べて食事をした。それは丁度良い高さだった。
夜の食事の間は、電燈をその部屋に移動させ、終われば居間の方に移した。紐が長かったので、移動は簡単だった。
一つの電燈の下で、母は和裁の夜なべをするし、私は一方の隅で机に向かって勉強した。また、一方の隅では、祖母の同行の人たちが毎晩のように、二人三人は来て、仏教の話を聞いていた。冬は、火鉢を囲んで、騒がしく話し込んでいた。
私は自分の勉強より、祖母たちの話に気を取られ、仏教の話は嫌でも覚えた。
私はそんな騒がしい雰囲気が嫌だとは思わなかった。そんな騒々しい中での勉強が、性に合っていたのかも知れない。小学校六年までは、級長と副級長で通したからである。
母の夜なべの終わるのを待って、十時か十一時頃共同風呂に行った。しまい風呂は濁っていて独特の臭いがしていた。浴槽は大きいので、冬などはよく温まったが、北風の中を帰ってくると、手拭はピンと凍っていた。家から風呂までは、五分位の距離だったが、私の家は村の端に、中尾の山を背景として立っていて、特に寒かったのだと思う。
「風呂に入っても何にもならん。手も足もこんなに冷たくなった。」
私は家に着くなり、火鉢の残り火に、手をかざしながら言った。
「寝たら直ぐ温もるよ、体の芯が温まっているから。」
と、母は言ったが、朝まで温もらぬ夜もあった。
私は、この暗い家で、夜便所に行くのが怖くてたまらなかった。月夜の晩は大分明るかったが、普段は薄ぼんやりと、部屋の灯りがある程度なので、帰るときは後ずさりして、障子をバタンと閉めて部屋に戻った。
度々大きな従兄弟たちが来て、わざと怖い話を面白がって話した。私は怖いので手で耳をふさいでいたが、それでも時々手を放して聞いた。雪駄の音が、パタンパタンと、後から着いて来るとか、暗い中で顔やお尻を撫でられたと、得意になって話した。
私は便所に行くのを、いつも布団の中で、ギリギリまで我慢していた。この頃からの恐怖心は、大人になってからも続いているようである。
さてわが家も、兄が卒業してからは、村の出方になるべく、兄が出るようになった。
母の出る時は、半人前支払っていたのが、兄は男だから一人前で通った。
「うちもやっと男所帯になったね。」
母のこの一言は、十五・六年の間の母の感慨であり、願望だったと思う。
私の家は決して、金持ちではなかったが、思いやりのある兄と、優しい母と、信仰の熱い祖母との暮らしは幸せだった。