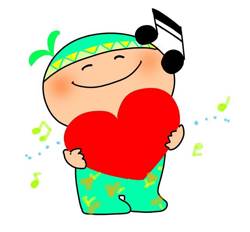昭和二十年の八月、突如詔勅が下がり、終戦を迎えた。
国民皆大きなショックを受けた。勿論、敗戦の悔しさはあったが、兎に角、戦争は終わったという、ほっとした気持ちもあった。
しかし、一方では、アメリカ兵が上陸して来て、女や子供はむごい目に遭うという噂も流れた。竹槍などを準備して、その日のための訓練も始終行われた。
結果としては、そんなことは何も起こらなかった。
戦時中は学童疎開や、田舎の親類、縁者を頼って疎開する人たちが多く、終戦後は猶更田舎に引き揚げる人達が多かった。
私の家にも、いくつかの家族が頼ってきた。どこも、子供が多く、食料もなく、金も乏しかったと思う。
私の従妹も八幡から、家族六人引き揚げてきた。皆、栄養失調気味で、殊に父親である従兄は、既に病身で、娘の一人も、胸を患っていた。近所の空き家を相談して借り受け、少々手を加え住まわせた。食料の調達にも気を使った。病人に必要な魚も卵もなかなか手に入らず、鶏を飼っている農家から、卵を少しずつ分けてもらうのが関の山だった。米を分けてもらうには、金では喜ばず、衣類など見繕って、交換したものだった。
従兄の次女は、病気がちだったが、大変美人だった。長女は既に他界していた。その娘も美人だった。引き揚げて来た年、次女美恵子は十七歳で他界した。
助からぬことはすでに本人も、知っていたらしく、死の際に、
「お母さん、天国とはどんなところでしょうね」
かすかな声で言った言葉を、私は生涯忘れられない。白蟻のように白く、清らかで世間の汚れを知らぬ娘の死は、神々しいほどだった。静かな死であった。
今は結核はほとんど治るが、当時は薬もなく、栄養を取ることもできなかったので、こういう死が沢山あった。
終戦の年、夫の戦友の西隈さんが、家族五人で大阪から引き揚げて来た。この人達も病人こそ居なかったが、体一つといたようなものだった。仕方なく、この人達の住む所を探して上げねばならなかった。私たちの仲人の野中さん宅の小屋が空いていることを思いつき、相談したところ聞き入れて下さったので、差し当たり大工を入れて、五人がどうにか住めるようにした。
私たちは従兄の家族にも、西隈さんにも、自分達で出来るだけのことはしてあげた。
終戦となり、我が家に出入りしていた兵隊さんたちも除隊となったが、都会の家は焼けているので、帰る家の無い人もあった。
源田少尉や、上田上等兵などは、仕方なく、私たちの工場で、働いてもらうことになった。主にトラックの運転である。
当時は木材の需要も増え、私達の工場も忙しくなった。女の事務員の馬場たみえさんも居た。この人は二年後、私達の世話で、日田の金川材木店に嫁いだ。
さて、私達の家も人の出入りが多く、食事時など、誰だかよく分からぬ人も食べていた。出来るだけ多くの人を、助けることが出来たのも、仕事が順調に行っていたからである。
夫は機械が大好きだから、いろいろ不思議なものをよく作った。
或る時、トレーラーを作った。これは山から長材を搬出するためで、自動車の運転台と長い車体を続かせており、電柱の八間物や、十間物など、山からこの車で工場まで運搬した。人々は珍しがって眺め、遠くから来ているのに、道をよけて待っていたりした。
今、こんなトレーラーは、珍しくもなく、何処にでもあるが、当時としては、見たこともない物だった。
少し後にジープも作った。ガソリンも配給だったので、薪の火力で動く木炭車だった。
その頃バスも作った。片側に五人ずつ掛けられる十人乗りだった。
ポンポンと音を立て、黒い煙を出して走るので、遠い所からも、その音が聞こえ、人々は野村のバスが走っていると噂した。
さて、私も一男三女の母親となり、生活にも多少はゆとりが出来てきた。
工場の空き地も広がったので、子供たちは土にまみれて伸び伸びと育っていった。
しかし、住いだけは手狭で、間に合わせの家だったので、荒削りの柱があったり、板張りも十分削ってないのが打ち付けてあったりした。台所の柱など上の方に、杉皮が多少残っていて、早く言えば、気の利いた小屋みたいなものだった。
昌三が五,六歳になると、その柱に登り、ナイフでその杉皮を削り落としていた。
「昌三、あんまり削ると、柱が倒れるよ。」
「柱が倒れたらどうなるの?」
「柱が倒れたら家が倒れるじゃあないの。」
これは、おばあちゃんと孫との会話である。
夫はどの子も大変可愛がった。夕方になり、仕事が終わると、どの子もよくおんぶされていた。
「お父さん、向こう向いて」
夫が背を向けると、後ろから背中に飛び掛かっておんぶされた。五,六歳になっても、このおんぶを四人とも楽しんだ。
夫は飛び掛かってきた子をおんぶして、ぶらぶら広い工場の空き地を歩き回っていた。
夫は写真の趣味もあり、高価なライカを持っていて、現像から焼き付けまで、全部自分でやるので、道具も一式揃えていたし、暗室も作っていた。
「今夜は現像するぞ。」
という日は、夕食もそこそこにし、私も手伝い、自分たちの写った写真の出来栄えを批評し合って、夜更かしすることも度々あった。
戦前の写真は、防空壕で駄目にして、戦後のものは水害に遭い、水浸しになったので、子供たちの育ちざかりの貴重な写真を失って、悔やまれてならない。
我が家には通勤の従業員の外に、住込みの氷室という男が居た。この人は、多少小児麻痺気味で、言葉もゆっくりしか話せず、片足を横に少し降るようにして歩いた。彼は手使いで小屋の方に、一人で住んでいた。
浩ちゃんという青年も住込みだった。この人は夫の従兄で、背の高い色白の、良い男だった。
それに、チビの俊ちゃんが居た。この子は同じ村だったので、通勤していたが、食事は家で三食食べていた。小六を卒業してきた子で、小さく痩せていて、リスのように身軽く、飛び回っていた。夫も、「俊、俊」といって、可愛がっていた。
秋になると薩摩芋を、何百キロと買ってきて、工場の空き地に穴を掘り、もみ殻の中に芋を積み込み、藁屑をかぶせて冬まで備えた。
蜜柑も収穫期にはトラックで買ってきて、これは杉の生葉の中に包みこみ、上から藁屑をかぶせた。こうして、保存すると、春まで新鮮さを失わず、甘みも増していた。
また工場の近くには、葡萄園や梨畑が沢山あり、果物には恵まれていた。
秋の終わりに収穫する梨に、三吉というのがある。大玉で保存がきくので、毎年百キロ、二百キロと買い込み、大きな甕(かめ)に保存した。
この甕の大きさは、高さ一メートル五,六十センチ、直径七十センチほどあり、梯子を使って、梨を出し入れした。
甕の底から、一尺位の所まで水を入れ、その上に気の蓋を水につからぬ程度に敷いた。蓋には直径二センチの穴を四,五センチ間隔にくり抜いていた。その蓋の上に梨を積み重ねてゆく。そして、甕の上部の口は密封しておく。
これは毎年、私の仕事だった。
この梨は、春四,五月頃取り出し、贈り物や見舞いなどにして喜ばれた。
冬は、工場の裏の空き地で、毎日朝から晩まで焚火が絶えなかった。
焚火の中に、藁屑の中から出してきた芋を、大かごいっぱい放り込み、工場の休憩時間には、皆で焚火を囲み、芋を食べながら談笑した。
この頃かった山林は、順調に利を生み、野村製材所も、少しずつ大きくなっていった。
蜜柑の時期には、蜜柑山に、友人、知人、銀行員や、学校の先生方を招待した。弁当は仕出し屋に注文し、時には芸者を連れて行き、山で酒宴を張った。また、松茸山を一山買い切り、日頃お世話になっている商売関係の人や、それ以外の関係の人々を招待して喜ばれた。これこそ、田舎の醍醐味で、都会では味わえない楽しみであった。